近年、1980年代のシティ・ポップが再ブームになったことが記憶に新しいですが、山下達郎や松原みき、竹内まりやなどの陰に隠れ、唯一無二の音楽性を持つバンドが存在していたのをご存知でしょうか?
それが、「1986オメガトライブ」(1986〜1991)です。
この記事では、そんな1986オメガトライブの独自性について、主に制作陣に注目しながら、ファンである私が語ります。
メンバー
本記事の主題は制作陣なので、メンバーは簡単に触れておきます。
※もっと詳しく知りたい方は別記事で紹介予定です。
・カルロス・トシキ(Vo.)
・高島信二(Gt.)
・西原俊次(Key.)
・黒川照家(Gt.)※1988年に脱退
・ジョイ・マッコイ(Cho.)※1988年に加入
制作陣
次に、この記事のメインである制作陣について紹介します。
こちらが、1986オメガトライブの主な制作陣です。
作曲:和泉常寛
作詞:売野雅勇、有川正沙子
編曲:新川博、船山基紀
プロデュース:藤田浩一
1986オメガトライブは、前身バンドである『杉山清貴&オメガトライブ』の体制を引き継ぎ、作詞・作曲・編曲は、主にメンバーではなくプロが担当していました。
今回はサウンド面に絞っているため、作詞については詳しく触れません。
売野さん・有川さんにも敬意を表しつつ、また別記事で扱えたらと思います。
作曲:和泉常寛
1986オメガトライブの作曲は、主に和泉常寛さんが担当していました。
和泉さんは、フォークデュオ出身でレコードデビューもしています。
和泉さんの曲は、転調や複雑なコード進行が特徴です。
にもかかわらず、違和感のない美しさがあり、リスナーを飽きさせません。
『Stay Girl Stay Pure』という曲は、和泉さんの転調センスが典型的な曲です。
サビでの転調によって、独特の浮遊感があり、他のシティ・ポップとは違った美しさを感じます。
ピュアな歌詞に対し、洒脱な曲調が最高で、非常に完成度が高い一曲です。
和泉さんは、ボーカルであるカルロスの持ち味を誰よりも理解し、それを最大限に引き出す曲作りに徹していたのでしょう。
実際にカルロスは、和泉さんの曲を歌うときに一番生き生きとしていたのは、明らかです。
1986オメガトライブは、活動後期に林哲司さんや松任谷由実さんといった大物作曲家にも曲を提供されており、それらの楽曲自体は素晴らしいのですが、カルロスの歌唱とは、どこか噛み合ってない感じが否めません。
カルロスには、洋楽寄りでダンサブルな曲が合うのでしょう。和泉さんの仕事には脱帽します。
編曲:新川博
1986オメガトライブの編曲は、主に2人体制でした。
その1人であり、藤田プロデューサーとともに、1986オメガトライブのサウンドの核を担ったのが、新川博さんです。
新川さんはキーボーディストであり、編曲だけではなく作曲も手がけます。過去には荒井由実のコンサートの音楽監督もしていました。
『Cosmic Love』という曲は、新川さんのアレンジのセンスが目立ちます。
この曲が制作された当時、1986オメガトライブは、新しい音楽性を開拓したいという試みがあり、この曲が作られたそうです。
この曲のビートは、他の楽曲と一線を画す、宇宙を感じるような構成となっています。
編曲:船山基紀
1986オメガトライブの編曲を担ったもう1人が、船山基紀さんです。
船山さんは、日本の編曲家として最も有名なのではないでしょうか。
『勝手にしやがれ』や『Romanticが止まらない』など、手掛けたヒット曲は数えきれません。
1986オメガトライブにおいても、船山さんが担当した楽曲は、派手なアレンジが特徴で、聴いていて楽しいものが多いです。
『Navigator』という曲は、歌詞でもメロディーでもなく、アレンジが主役といってもいいほどの曲です。
藤田プロデューサーが、この曲には新しいアレンジを求めたそうで、何度も試行錯誤をしながら、船山さんによってアレンジされたそうです。
プロデュース:藤田浩一
1986オメガトライブの曲には、藤田浩一プロデューサーの意向が強く反映されているということも、忘れてはいけません。
藤田プロデューサーは、「ブラックミュージック好き、ロック嫌い」なことで有名で、「トライアングル・プロダクション」のアーティストは、ブラックミュージック路線ばかりでした。
菊池桃子率いるラ・ムーも、「ロック・バンド」だと名乗っていましたが、例外なくバリバリのブラック・コンテンポラリーでした。
そんな藤田プロデューサーのブラックミュージックに対する愛と、完璧主義な性格は、1986オメガトライブの音楽性に直結したと言っても過言ではないでしょう。
独自性についての考察
冒頭でも少し言及しましたが、1986オメガトライブは、「王道シティ・ポップ」とは、少し違う独自性を持っていると思います。
それがどこなのか、素人なりに分析してみた結果がこちらです。
【1986オメガトライブの独自性についての考察】
♫ ビートが強く複雑だが、一曲の中でほぼ一貫しているため踊りやすい
♫ メロディーは、邦楽寄りで口ずさみやすい
♫ コード進行の展開が早め
♫ ブラスは、生楽器の代わりにシンセサイザーを使っているため、ポップス感と清涼感が強い
♫ ギターのカッティングが控えめ
♫ 作曲者、編曲者が曲によって異なるも、サウンドが統一されている
♫ 全体的に鋭すぎる音色が抑えられており、聞き馴染みが良い
1986オメガトライブの曲は、当時のシティ・ポップとしては珍しく、打ち込み主体でシンセサイザーが多用されています。
音色だけを聴くと、アイドルソング寄りのポップスだと思ってしまいますが、リズムとコード進行はブラックミュージック寄りです。
「音は柔らかく、リズムとコードは黒い」
これが、1986オメガトライブの最も大きな独自性だと考えます。
ポップスの皮を被ったバリバリのブラックミュージックですね。
まとめ
1986オメガトライブは、時代の先を行く音楽性を持ちながら、その革新性が十分に語られてこなかったように思います。
昭和を振り返る音楽番組でも、『君は1000%』を除いてあまり取り上げられないのも悲しいです。
しかし、80年代特有の煌びやかなサウンドでありながら、40年経った今でも安っぽく感じることがないのは、当時の制作陣のセンスと努力の結晶だと言えるでしょう。
もし、この記事を見て1986オメガトライブに興味を持っていただけたなら、是非聞いてみてほしいです。
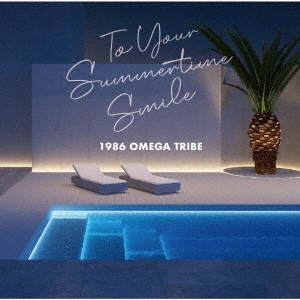
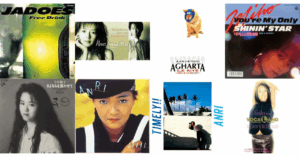

コメント